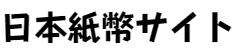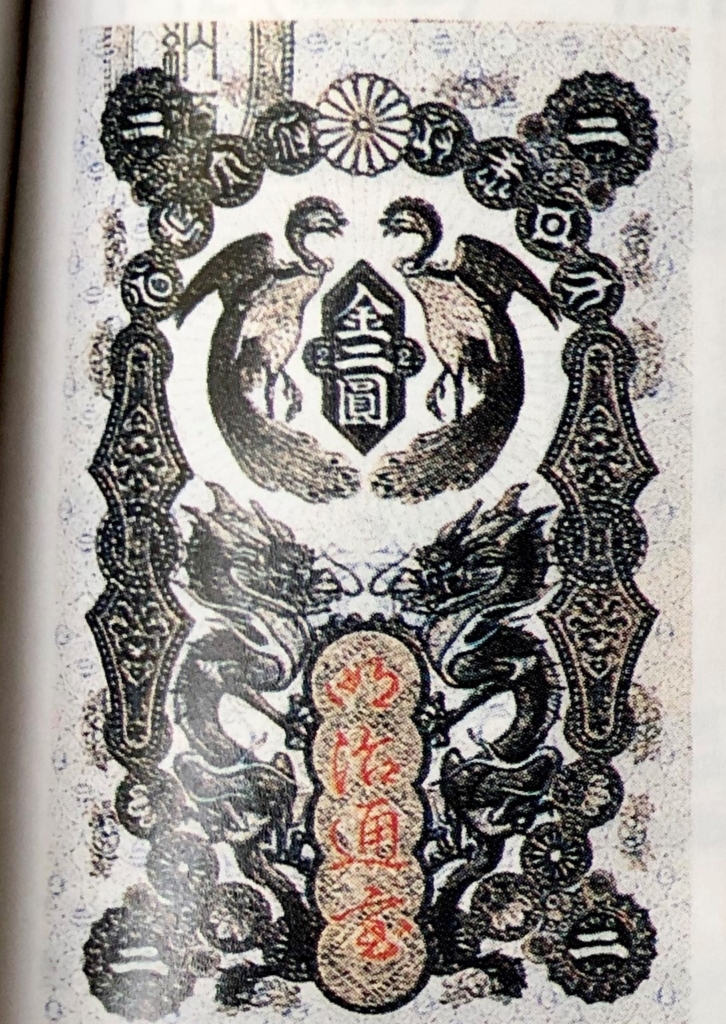日本で初めて発行された紙幣は、いつできたのか?どんなデザインなのか?どんな時代だったのかをお伝えします。

案内人の諭吉くんだ。
これから日本紙幣について勉強していくよ。
オイラはどら猫くんだ。
これから諭吉先生に色々教わる猫だぞー。


では、本題に入るよ。
日本紙幣が最初にできたのは、いつだと思う?
弥生時代かー?いや平安時代だぞー!


随分さかのぼりましたね。
答えは明治時代です!
目次
初めての日本紙幣は明治時代に発行された
そう、日本紙幣の始まりは明治時代。
明治新政府によって、ドイツに印刷を依頼して1億5千枚分を発行したんだ。
初めて発行された日本紙幣ってどんなものだったのか見ていこう!
初めての日本紙幣はどんな紙幣だったの?
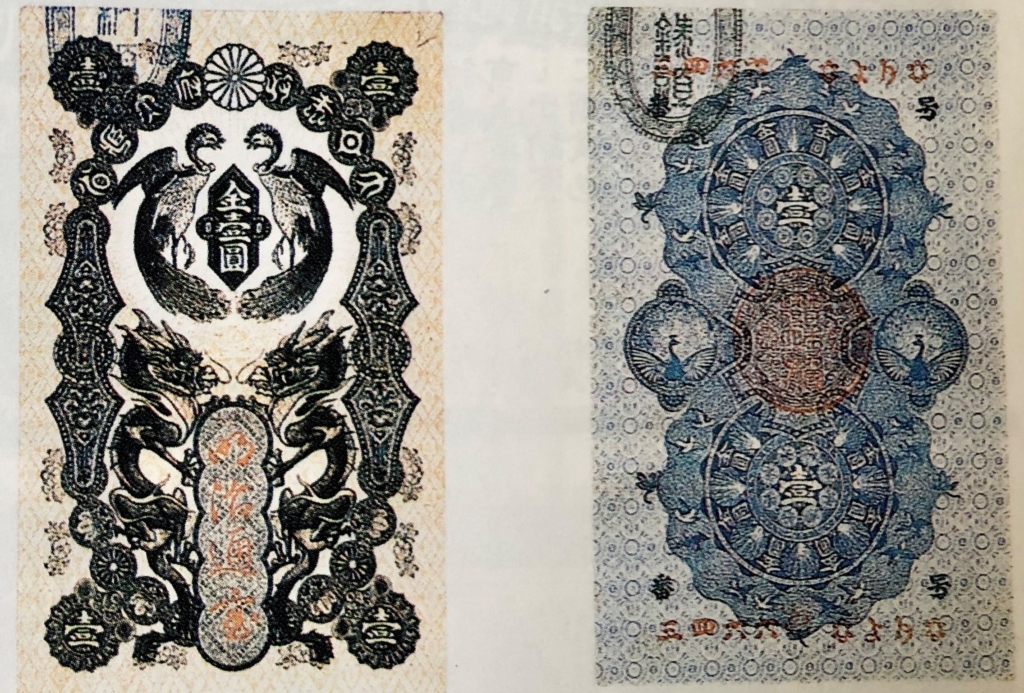
1枚目の写真は明治通宝1円だよ。
鳳凰と竜の絵がかっこいいね。
初めての紙幣でこのクオリティは素晴らしいと思わないかい?
明治通宝の文字は最初は手書きでされていたが、途中から木版に変えたそうだ。

左が明治通宝半円/右が明治通宝20銭
1円と20銭の間に半円という紙幣があった。

明治通宝10銭
見た目がどれも似ていて間違えて支払ってしまいそうだね。
ここまでの明治通宝1円~10銭の発行日と廃止日をまとめたよ。
明治通宝1円 【発行】明治5年2月15日 【廃止】明治32年12月31日
明治通宝半円 【発行】明治5年2月15日 【廃止】明治32年12月31日
明治通宝20銭 【発行】明治5年2月15日 【廃止】明治32年12月31日
明治通宝10銭 【発行】明治5年2月15日 【廃止】明治20年6月30日
初めての日本紙幣はこの4枚になるけど、その後にも同年に続々と紙幣ができたんだ。
同じ年に発行された日本紙幣
左は明治通宝10円 / 中は明治通宝5円 / 右は明治通宝2円
この紙幣も同じデザインだね。
明治通宝10円 【発行】明治5年6月25日 【廃止】明治32年12月31日
明治通宝5円 【発行】明治5年6月25日 【廃止】明治32年12月31日
明治通宝2円 【発行】明治5年6月25日 【廃止】明治32年12月31日

左 明治通宝100円 / 右 明治通宝50円
明治通宝100円 【発行】明治5年8月13日 【廃止】明治32年12月31日
明治通宝50円 【発行】明治5年8月13日 【廃止】明治32年12月31日
明治通宝10銭以外は、全て明治32年の12月31日で廃止になったんだね。
27年も同じ紙幣が使われていたなんてスゴイことだと思わないかい?
では、この頃にはどんなことが起こっていたのか一緒に覚えていこう!
この頃の出来事
私事だが『学問ノススメ』が発行された年だよ!350万部も売れて驚いたねぇ。
明治5年に義務教育が出来た。
意外と早くから義務教育は存在していたんだ。
他には、この年の12月は2日しかなかったようだよ。
え?12月が2日しかなかったってことかー?

明治5年の12月に天保暦から西暦に変わり、12月3日が明治6年の1月になってしまったんだ。
天保暦というのは、太陽陰陽暦のことで簡単にいうと月の満ち欠けや太陽の動きで1か月や1年を計算していた。それを西暦に改暦し1日24時間と時間を定めるようになったんだよ。
12月生まれの人は誕生日ケーキが食べれなかったってことかー。
可哀想だぞー。


うむ。
今日の授業はここまでだ。
明日からは人物が出てくるから、少し楽しめると思うぞ。
どら猫くんは予習してくるように!
ええー!オイラこれから夜の集会なのにー!

次回もお楽しみに!
参考文献:日本貨幣カタログ2019