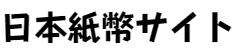ヤマト政権の氏と姓や、構造など図を用いてわかりやすくお伝えします。

ヤマト政権は3世紀後半~7世紀中盤の政権になるぞ。
(古墳が存在していたのが3世紀後半~)
すごい昔だなー!
オイラ蘇我氏しか知らないやー。

蘇我氏とは、馬子・蝦夷・入鹿で有名な氏。
他には、どんな氏の人が活躍していたのか、知っているかね?
それでは、豪族の氏と姓について、わかりやすく説明しよう。
目次
ヤマト政権の豪族
ヤマト政権は、氏と姓で豪族の地位を表していた。
《氏の2パターン》
①本拠地名が氏の名前になる
蘇我(そが)
葛城(かつらぎ)
平群(へぐり)…などなど他の氏も有り
②職業が氏の名前になる
大伴(おおとも)・・・伴造を統活
物部(もののべ)・・・軍事
中臣(なかとみ)・・・祭祀(神)
…などなど他の氏も有り
※伴造(とものみやっこ)は、大王(天皇)に奉仕する者である。
《姓(かばね)~大王(天皇)により与えられた家格の称号 》
| 姓(かばね) | 豪族地位 |
|---|---|
| 臣(おみ) | ヤマト地方の最有力氏 |
| 連(むらじ) | 特定職位を持つ有力伴造 |
| 君(きみ) | 地方有力豪族 |
| 直(あたえ) | 国造に任じられた地方豪族 |
| 造(みやっこ) | 伴造の首長 |
| 首(おびと) | 伴造豪族 |
| 史(ふひと) | 文筆・記録を行う帰化人 |
| 村主・勝(すぐり) | 中小豪族の帰化人(朝鮮) |
※史と村主・勝は書籍に登場しないことが多い。
※赤字は政権トップの氏。その中でも更に上の大臣と大連がいた。
実際はどんな風に呼ばれていたんだー?

実際には、このように呼ばれていたんだ。
氏+姓+名前
《例》
蘇我 臣 馬子 蘇我氏でヤマトの有力豪族の馬子
中臣 連 鎌足 中臣氏で祭祀担当の鎌足
氏について説明したが、先ほど表記した6つの氏以外にもたくさんいたんだ。
一つ一つ、深堀りしていこう。
ヤマト政権の氏1【大臣・大連に関わる氏】
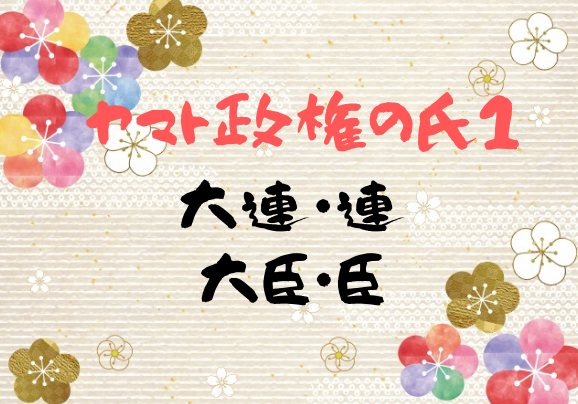
大臣(おおおみ)の氏
- 蘇我氏(そが)
- 平群氏(へぐり)
- 葛城氏(かつらぎ)
- 巨勢氏(こせ)
…など
【例】巨勢 大臣 ◯◯
臣(おみ)の氏
- 紀氏(きの)
- 波多氏(はた)
- 阿部氏(あべ)
- 穂積氏(ほづみ)
- 春日氏(かすが)
…など
【例】紀 臣 ◯◯
臣は、連と並び最も高い位に位置する氏である。
大連(おおむらじ)の氏
- 大伴氏(おおとも)
- 物部氏(もののべ)
…など
【例】大伴 大連 ◯◯
連(むらじ)の氏
- 中臣氏(なかとみ)
- 土師氏(はじ)
- 弓削氏(ゆげ)
- 尾張氏(おわり)
- 忌部氏(いんべ)
- 犬養氏(いぬかい)
- 舂米氏(つきしね)
…など
連は、祭祀を担当していた氏が多かった。
【例】土師 連 ◯◯
蘇我氏と物部氏の先祖は宿禰の称号が与えられていた(先祖は武内宿禰)。
あ!犬養氏って犬養毅の?
こんな昔から権力者だったんだなー。


そうですね。
生まれつき権力がなく、努力した私から見たら腹が立ちますが…。
ヤマト政権の氏2【国造(くにのみやっこ)に関わる氏】

国造(くにのみやっこ)の氏
国造は地方国の長官。
地方の豪族や中央から派遣される。
中には朝廷に歯向かう者もいた。
国造の部下は県(あがた)。
- 出雲(いずも)
- 牟邪志(むさし)
- 遠代(とおしろ)
- 甲斐(かい)
- 茨城(いばらき)
- 山代(やましろ)
- 周防(すおう)
- 伊余(いよ)
- 科野(しなの)
- 木(き)
- 筑紫(つくし)
- 日向(ひゅうが)
- 尾張(おわり)
- 相武(さがむ)
- 讃岐(さぬき)
- 美濃(みの)
- 吉備(きび)
…など
【例】尾張 国造 ◯◯
君(きみ)または公(きみ)の氏
- 息長氏(おきなが)
- 上毛野(かみつけの)
- 下毛野(しもつけの)
- 多治比氏(たじひ)
- 当麻氏(とうま)
…など
【例】当麻 君 ◯◯
直(あたえ)の氏
- 凡氏(おおし)
- 舎人氏(とねり)
…など
【例】舎人 直 ◯◯
ヤマト政権の氏3【伴造に関わる帰化人(渡来人)の氏】

帰化人(渡来人)とは、中国や朝鮮から渡って来た者である。
伴造に関連する氏は帰化人(渡来人)ということ。
伴造に関わる豪族
造・首・史・村主
伴造(とものみやっこ)の氏
- 秦氏(はた)
- 東漢氏(やまとのあや)
- 西文氏(かわちのふみ)
…など
【例】秦 伴造 ◯◯
造(みやっこ)の氏
- 水取氏(もひとり)
- 矢田部氏(やたべ)
- 藤原部氏(ふじわらべ)
- 刑部氏(おさかべ)
- 福草部氏(ささくさべ)
- 殿服部氏(とのはとりべ)
- 錦織部氏(にしこりべ)
- 縵氏(かずら)
- 鳥取氏(ととり)
- 忍海氏(おしぬま)
…など
【例】刑部 造 ◯◯
首(おびと)の氏
- 西文(かわちのあや)
- 韓鍛冶(からかぬち)
…など
【例】西文 首 ◯◯
史(ふひと)の氏
漢字の伝来により、文筆や記録を任された渡来人。
- 田辺(たなべ)
- 阿直岐(あちき)
- 船(ふね)
- 白猪(しらい)
…など
【例】船 史 ◯◯
村主・勝(すぐり)の氏
祖は東漢氏であるが、秦氏の支配下で首長を務めていた人たち。
- 桑原(くわはら)
- 高向(たかむこ)
- 阿知(あち)
【例】桑原 村主 ◯◯

次は、ヤマト政権の構造について見てみよう!
ヤマト政権の構造
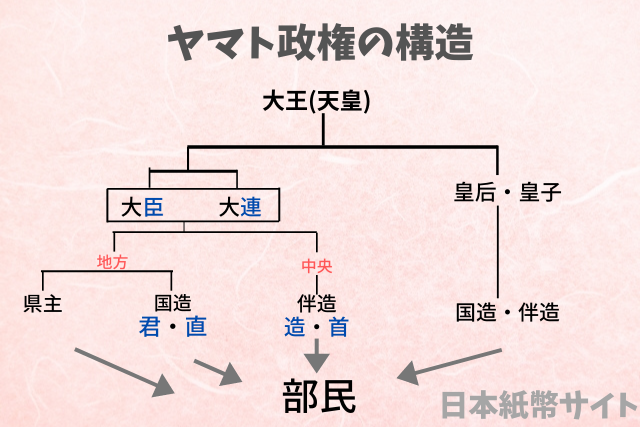
大王(天皇)の下には、大臣・大連がいて、その下は中央(朝廷)と地方の中間管理職であった。
さらに下に位置する『部民』というのは、豪族が所有する私有民のことである。
かつて、私有民に関して問題になった時代があった。
こちらの藤原鎌足(中臣鎌足)の記事を、見て欲しい。
-

-
改造兌換銀行券100円 めがね100円【藤原鎌足】と大津事件
明治24年に発行された改造兌換銀行券100円(100円札)に描かれた人物と、発行年の出来事をわかりやすくお伝えします。 諭吉くん今日は改造兌換銀行券100円の勉強をするよ。 改造兌換銀行券はこれが最後 ...
続きを見る
この他に、天皇が病弱であったり子供の場合の『摂政』という地位もあった。
摂政は天皇の代わり(や共)に政治を行う人なので、大臣や大連より上の立場になる。
摂政についた有名な人
・聖徳太子(初)
・中大兄皇子
・藤原忠平


ちなみにヤマト政権は古墳時代と飛鳥時代に渡り、続いたよ。
なにがキッカケで終わったんだー?


645年の大化の改新で、ヤマト政権が終わったんだよ。
大連という役職がなくなり、代わりに右大臣・左大臣が配置された。
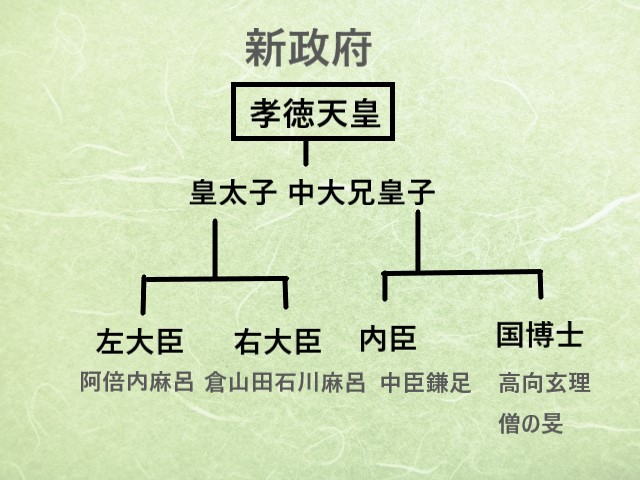
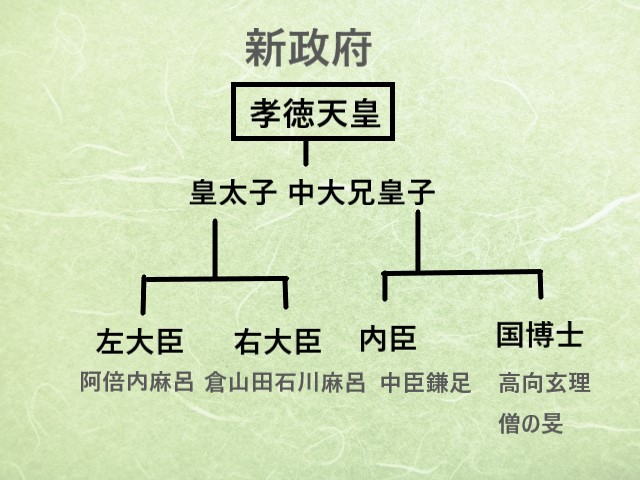
ここまでが、ヤマト政権についてのまとめだ。
時代は3世紀後半~7世紀中盤になるよ。
関連する聖徳太子の記事はこちら
-



-
紙幣になった【聖徳太子】は何をした人なのか歴史をわかりやすく学ぶ
日本紙幣に登場する聖徳太子は、一体どんなことをした人物なのかを、まとめた記事になります。 諭吉くんどら猫くん、今日は聖徳太子についての勉強だよ。 おぉー!オイラ聖徳太子の順番が来るのを楽しみにしてたぞ ...
続きを見る
最後に・・・
大和朝廷ではなく、なぜヤマト政権なのか?
- 大和は日本のこと。なので近畿地方中心の政治なのでヤマトになった。
- 朝廷というのは、天皇が行う政治なので微妙に当てはまらない。
大和朝廷というのは、死語になってしまったんだ。
正しくは
・ヤマト政権
・ヤマト王権 👈一番マスト★


時代と共に、歴史の内容も少し変化することがあるので注意しよう。
※今回は王権ではなく、あえて『政権』で統一。
参考文献:Wikipedia,歴史が面白いシリーズ!図解 日本史,詳説 日本史図録,古代をつくった人々 推古天皇・聖徳太子