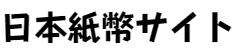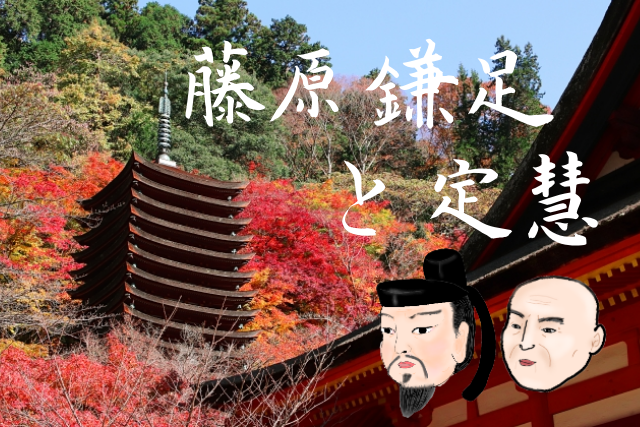
昭和6年に発行された兌換券20円(20円札)に描かれた人物と、発行年の出来事をわかりやすくお伝えします。

今日は、ある親子の物語を勉強するよ。
親子?んー誰だー?

兌換券20円の人物・藤原鎌足(中臣鎌足)には息子が2人いたんだ。
今回は長男・中臣真人(なかとみのまひと)との関係性も一緒に学んでいこう。
目次
兌換券20円 タテ書き20円


紙幣の説明
他の兌換券と同様に、昭和2年に法案された『兌換銀行券整理法』に基づいて発行されたお札である。
兌換銀行券整理法とは、時代に合った価値の紙幣を作るという法になるよ。
昭和6年の出来事
昭和5年に濱口雄幸首相が右翼団体に襲撃されて、翌年に死去。
内閣総理大臣には若槻禮次郎(わかつきれいじろう)が就任。
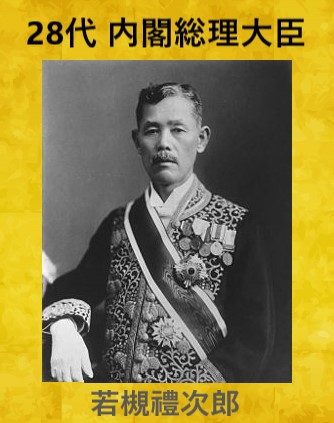
昭和6年になると3月・10月に日本陸軍がクーデターを起こそうと計画した。
三月事件・十月事件とよばれているが、どちらも未遂で終わった事件だ。
クーデターとは、暴力によって政治を変えようとすること。
なんでそんなことしたんだー?

軍事政権に変えたかったからだよ。
(日本軍が政治を行うこと)
未遂事件には、日本陸軍の他に右翼団体と社会民衆党も関わっていた。
若槻禮次郎は不運なことに、国内だけでなく国外でも問題を抱えていたよ。
-

-
昭和6年の出来事【満州事変】をわかりやすく知る|石原莞爾の未来構想
昭和6年に起こった満洲事変をわかりやすくお伝えします。 諭吉くんどら猫くん、今日は満洲事変について勉強するよ。 まんしゅうじへん?聞いたことあるけど、オイラよくわかんないぞー。 どら猫くん まずは、満 ...
続きを見る
昭和6年12月
内閣総理大臣が、交代する。
若槻禮次郎内閣➡犬養毅内閣
29代目・犬養内閣の大蔵大臣は、高橋是清が就任した。
高橋是清は民衆に人気があり『ダルマさん』の愛称で呼ばれていたんだよ。
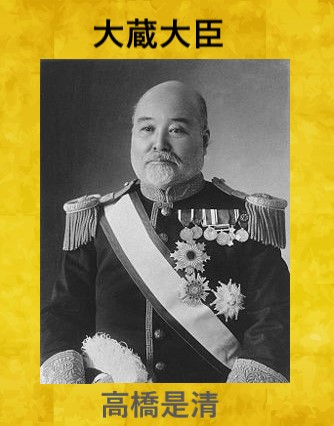
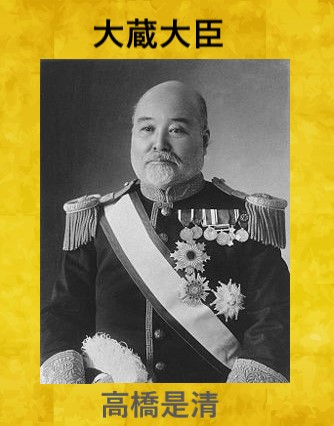
表で近年の内閣総理大臣と大蔵大臣を見てみよう。
| 内閣総理大臣 | 大蔵大臣 | 経済政策 | |
|---|---|---|---|
| 26代目 | 田中義一 | 高橋是清 三土忠造 | ・金本位制と金輸出を見送る ・大量に紙幣を刷り(裏白)、銀行を救う |
| 27代目 | 濱口雄幸 | 井上準之助 | ・金本位制に戻し金輸出解禁 |
| 28代目 | 若月禮次郎 | 井上準之助 | ・継続 |
| 29代目 | 犬養毅 | 高橋是清 | ・金本位制廃止と金輸出の禁止 ・実質的な管理通貨制度の導入※ |
※管理通貨制度とは、通貨の発行量を調節し経済成長や物価の安定を図る制度のこと。
高橋是清は26代目・田中義一内閣でも大蔵大臣を務めており、金本位制をしない方針だった。
犬養毅内閣で大蔵大臣に就任されると、その日に『金輸出の禁止(許可制)』をし金本位制を廃止させた。


さて、どら猫くんは金本位制を覚えているかな?
えっ?!…んとーんとー忘れたぞー。




金の価値に合わせた基準の紙幣価値のこと。
金本位制について詳しく書かれた記事はこちらだぞ。
-



-
甲号兌換銀行券5円 中央武内5円【武内宿禰】と領事裁判権・治外法権
明治32年に発行された甲号兌換銀行券5円(5円札)に描かれた人物と、発行年の出来事をわかりやすくお伝えします。 諭吉くん今日から甲号兌換銀行券の勉強だよ。 兌換が続くなー。 どら猫くん 甲号兌換銀行券 ...
続きを見る
金本位制が始まったのは、明治30年。
明治28年に日清戦争に勝利し、戦利品として大量の金を得て貨幣法が変更されたんだよ。
その後、第一次世界大戦開始後に金本位制を一度停止している。
しかし、濱口雄幸内閣で解禁してしまい、どんどん不況に陥ったんだ。
そして再び、昭和6年12月17日に日本銀行券の金への交換は禁止になった。
これにより、日本経済は右肩上がりに良くなり世界恐慌から抜け出したんだ。
えっ!高橋のおっちゃんスゴイぞー!


ここまでが昭和6年の出来事だよ。
兌換券20円に描かれたもの
【表】藤原鎌足と十三重塔(じゅうさんじゅうのとう)


藤原鎌足は、中臣鎌足のことだ。
有名なのが中大兄皇子とタッグを組んだ『大化の改新』。
蘇我入鹿を討った事件を大化の改新だと勘違いしてしまうが、あれは『乙巳の変(いっしのへん)』という。
藤原鎌足の基本情報は、こちらの記事の書いてあるぞ。
-



-
改造兌換銀行券100円 めがね100円【藤原鎌足】と大津事件
明治24年に発行された改造兌換銀行券100円(100円札)に描かれた人物と、発行年の出来事をわかりやすくお伝えします。 諭吉くん今日は改造兌換銀行券100円の勉強をするよ。 改造兌換銀行券はこれが最後 ...
続きを見る
-



-
甲号兌換銀行券100円 裏紫100円【藤原鎌足と談山神社】中臣から藤原へ
明治33年に発行された甲号兌換銀行券100円(100円札)に描かれた人物と、発行年の出来事をわかりやすくお伝えします。 諭吉くん今日は、当時1枚200万円の価値がある甲号兌換銀行券100円札を勉強しよ ...
続きを見る
表の左側にある建物は談山神社の十三重塔だ。


この十三重塔は、藤原鎌足の息子である僧侶の定慧(じょうけい)が造ったものなんだ。
冒頭で伝えた藤原真人が出家し定慧となったんだよ。
弟の藤原不比等(ふひと)と共に建てたという説もある。
父の墓を大阪府から奈良県の多武峰(とうのみね)に移し、そこに十三重塔を建てる。


親想いの息子たちで泣いちゃいますね。
701年には藤原鎌足の御神像を本殿に祀ったんだ。


【裏】談山神社


裏は、談山神社の拝殿が描かれている。
談山神社の『談山』には由来があるんだ。
中大兄皇子と多武峰の山に登って談合をしており、その山を『談い山』『談所ケ森』と呼んでいたそうだ。
そこから談山神社と名付けられたんだよ。
兌換券20円の人物が祀られた神社
談山神社(たんざんじんじゃ)


【談山神社 公式ホームページ】 http://www.tanzan.or.jp/
忍陵神社(しのぶがおかじんじゃ)
大阪府四條畷市にある神社。
藤原鎌足を主祭神として祀られている。
公式ホームページなし
大織冠神社(たいしょくかんじんじゃ)


大織冠って何だったか覚えているかい?
この時代の役人は帽子の色で地位を決めていたんだ。
その中で、最高位の『大織冠』を授けられたのが藤原鎌足だったね。
公式ホームページなし
【兌換券20円】まとめ
①発行日と廃止日
②発行年に起こった出来事
③紙幣に描かれた人物と関係者
①発行日と廃止日
兌換券20円【発行】昭和6年7月21日【廃止】昭和21年3月2日
②昭和6年に起こった出来事
- 三月事件
- 十月事件
- 再度の金本位制廃止
③兌換券20円に描かれた人物と関係者
【藤原鎌足】ふじわらの かまたり
・奈良に614年生まれる
・元の名は中臣鎌足
・中臣家は朝廷の神事を任された一族
・蘇我氏を排除するために中大兄皇子と団結し蘇我入鹿を討つ(乙巳の変)
・大化の改新を施行
・役人最高地位の大織冠を授けられる
【定慧】じょうけい
・藤原鎌足の長男の中臣真人
・僧侶
・父のために十三重塔を建てる
【藤原不比等】ふじわらのふひと
・飛鳥~奈良時代の公卿(くぎょう)→現:大臣のこと
・竹取物語の貴公子のモデルになった人物
【中大兄皇子】なかのおおえのおうじ
・奈良に626年に生まれる
・父は舒明天皇で母は皇極天皇(斉明天皇)←2回天皇になっている
・後に天智天皇となる人
・中臣鎌足に声をかけられて蘇我氏を討つことになる(乙巳の変)
・大化の改新を施行
・白村江の戦いも試みた
今日の勉強はここまでだよ。
次回は、昭和17年に発行された改正兌換券5円について勉強しようか。
次回もお楽しみに!
参考文献:日本貨幣カタログ2019,マンガ日本の歴史5 隋・唐帝国と大化の改新,詳説 日本史図録,お札になった人々,Wikipedia,談山神社公式ホームページ,浄土宋大念寺ホームページ